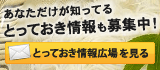縁起物 利田地区の秋祭り
2012年02月14日
神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 17:05 | Comments(0) | お祭り

11月23日に神埼の利田地区で行われた、秋祭りにお邪魔してきました。
お宮さん

利田地区は、公民館の中に社があり、養母神社(ヤフサジンジャ)と呼ばれ、地元の人に親しまれています。
古い文献では、八武佐(やぶさ)神・養父佐(やぶさ)大明神と記載されていることから、本来は「養父佐神社」と書いていたのではないかと思われます。
しかし、佐賀方言で、ヤブはヤボということから、転じて「養母」と書くようになったのではないでしょうか。

こちらでお祀りしてある神様は、日本武尊命(ヤマトタケルノミコト)です。
準備
準備は20日の朝、注連縄作りから始まりました。
地区の方が公民館に集合されました。
利田地区は、注連縄にはうるち米と餅米の藁を混ぜて使われています。

地区の方にお伺いしたところ、「餅藁は柔らかく、藁を巻きやすい。そして仕上がりが綺麗にできる。」と教えて頂きました。

この時期は色々な所で注連縄作りの調査をさせて頂いているのですが、地区によって材料や作り方に違いや特徴があったことがとても興味深かったです。


出来あがった注連縄は、公民館の中のお宮さんに飾りつけられました。

次に公民館入口に男竹と女竹を使って鳥居を作ります。

一般的なものはアルファベットの"H"のような形を作る文字通り鳥居のような形を作られることが多いのですが、この地区では、加えて中央に竹を交差させられています。

何を飾るのか見ていると、国旗を飾られていました。この日は勤労感謝の祝日ということもあり、飾られていたのでしょうか。

そして最後に根元に稲穂と、先ほどより少し細い注連縄を飾って鳥居の完成です。
鳥居の足に藁を巻かれることはよくあるのですが、稲穂まで飾りつけてあるのは、中々珍しいことだと思います。


今と昔
23日、公民館前に盛砂をし、注連縄に御幣を飾りつけると、お祭りの準備が整いました。
櫛田宮から宮司さんを迎え、太鼓の音と共のに、神事が厳かに始まりました。

今年一年の収穫を神様に感謝します。
その後、参拝者全員で直会(なおらい)が行われました。

以前は大人から子供まで地区全員が参加していたそうですが、現在は戸主の方が参加されているようです。
地区の方に、「昔は、祭り田と祭り堀があり、その収穫と、堀干しして獲れたドジョウやフナ、鯉を料理して食べた」と、教えて頂きました。
また、昭和35、6年までは、前夜祭をおこなっていて、その前夜祭の事を「やすまく」と呼んでいたそうです。
「やすまく」は、旦那衆の飲み会で、このときも堀干ししたドジョウ汁を食べていたそうです。
そして当日は、「朝5時から子供が太鼓をたたいて知らせ、施主宅で朝食、赤飯・塩いわしを、夕食は、朝の赤飯をもし直したものと、おかずを食べた。」と言われていました。
現在では、前夜祭や堀干しも行われていないので、祭りではドジョウ汁の代わりに豚汁と赤飯を食べるということでした。
縁起物を前に
直会も終盤に差し掛かかり、通渡しが行われました。
この通渡しは、今年の施主さんから、来年の施主さんへの引継ぎの行事です。
後日書類だけを渡したり、口頭で伝えたりと地区によって様々ですが、この地区では直会の最後に式を催されます。

ここでテーブルの上に持ってこられた物がこちらです。

神事の際にお供えされていたものですが、大根に松竹梅の枝が刺さっています。
参加者の方から「縁起物」と教えて頂きました。
この大根ですが、このお祭りのために作られているそうで、「何度も抜いて、植えてとても大変。中々3つに割れない。」とおっしゃっていました。
通渡しですが、前列に今年の施主さん、後列に来年の施主さんが座ります。
お酒を一口飲んだ後、お謡いをあげ、前後の列を交代して同じことを行います。

その後、今年の施主さんと来年の施主さんが、それぞれ挨拶をされてお開きとなりました。
時代に合わせて変わっていくものもありますが、「神事をして直会、その後に通渡しをする」という流れは、今でも変わっていないそうです。
区長さんをはじめ、地区の方々、ご協力ありがとうございました。