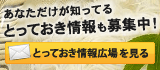上中下それぞれ 竹原地区の千灯籠
2011年09月22日
神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 17:30 | Comments(0) | お祭り
8月24日、竹原(たかわら)地区で行われた千燈籠にお邪魔してきました。
竹原地区では、上、中、下の3地区に分かれて、千灯籠が行われています。
「竹原は3ヶ所で千燈籠が行われていますが、何か理由があるのですか?」
と質問したところ
「特にはっきりとした理由はないけど、昔は子供の数が多かったから」
「もともと竹原は上、中、下の3つに分かれていて、それぞれにお祭りするご神像があったから」
とのお返事でした。
竹原地区では、上、中、下の3地区に分かれて、千灯籠が行われています。
「竹原は3ヶ所で千燈籠が行われていますが、何か理由があるのですか?」
と質問したところ
「特にはっきりとした理由はないけど、昔は子供の数が多かったから」
「もともと竹原は上、中、下の3つに分かれていて、それぞれにお祭りするご神像があったから」
とのお返事でした。
上地区
まずは、上(かみ)地区の千灯籠です。
主役の女の子たち。

みんな、豆詰めから接待と、遅くまでがんばっていました。
上地区では、お子さんが居る家が少ない為、できるだけ協力して一緒に準備をされています。

前日は、夕立ちの中、こころざしを集め、「千燈籠があるのでお参りしてください」と、声をかけて回られたそうです。
せっせと豆を詰め、あっと言う間に40袋出来ました。
豆詰めが終わったら、浄円寺の観音さんの飾り付けです。

女の子たちもお手伝いです。

さあ、日が暮れてきました。
提灯に明かりを灯して、参拝する人々を待ちます。

女の子達が、参拝に来られた方を一生懸命おもてなししていました。



中地区
つづいて中(なか)地区です。
中地区では、子どもが居ない為、大人の方が中心になっての千灯籠です。
中地区には、2か所のお堂があり、午前中には、施主の方がそれぞれのお堂を掃除し、花を供えられていました。



添えられた百合が綺麗です。
千灯籠につきものの煮豆は、微妙な味加減が難しいという事で、近所から助っ人を呼んでこられていました。


伝統の味はこうやって引き継がれていくのですね。
煮豆が出来ると、次は袋詰めです。

お参りされた方へのお土産に、他にも、キュウリとワカメの酢のものに竹の子の煮付などを一緒に用意されていました。

日が落ちるといよいよ本番です。

中地区では、お参りに来られた方がゆっくりできるよう、テーブルと椅子、雨除けのパラソルやテントまで用意されていました。


お堂の屋根には、暗い中お参りされる方が頭をぶつけたりしないよう、電飾で飾り付け。
ナイスアイデアですね

おもてなしの心が溢れる千灯籠でした。
下地区
最後に下(しも)地区です。
千燈籠には豆がつきもの。
下地区では、竹原公民館で当番にあたる女性が豆炊きをします。


夕方、豆が冷えたら子供たちが袋詰めをします。

「昔の千燈籠は、男の子のお祭りだったの。子供たちが、お金の集金からお堂での接待まで子供たちでしてたんだよ。」
「豆炊きも当番の班でしているけど、昔は、子供の親が炊きよった。昔はお祭りが終わった後、カレーを食べるのが楽しみだった。」
と、参加者の方が言われていました。
今は子供たちの数が減ったので、持ち回りで手伝いをされます。
また、接待も当番の方で行っているそうです。
こちらのお堂は去年完成し、千燈籠を行うのは2回目ということ。

幕を張り、電気系統の用意をしますので、男性が中心となって準備を進めます。
お堂の前のガードレールにちょうちんを飾ります。

石祠に天神様が登場です。

普段は施主の方が預かっているそうです。
この天神様、色は黒かったのですが、塗り直して金色になったとか・・・。
日が暮れて、参拝する人が来るのを待つのみとなりました。

時間となり、子供たちが「千燈籠があっているので、お参りに来てください。」と竹原地区を回って、参拝を呼びかけます。

参拝者は参拝が終わるとお堂の中で料理や飲み物をとりながら、談笑されています。

祇園祭りが、地域の人たちの交流の場にもなっているのですね

小さな子ども達には、豆のほかにお菓子のお土産があり、嬉しそうに持って帰っていました。

最後は子ども達が花火をしていました。
とても楽しそうです。


上、中、下、3地区それぞれ、地区ごとの違いがあり、非常に興味深く取材をさせていただきました。
夜遅くまでの取材となりましたが、区長さんを始め地区の方々、ご協力ありがとうございました。