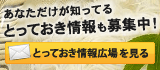娘別れと里帰り 大島の観音さん祭り
2011年08月26日
神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 18:22 | Comments(2) | お祭り

8月9日に、大島地区の菅原神社で行われた、観音さん祭りにお邪魔してきました。
観音さんお茶講
観音堂のお掃除から取材させていただきました。

しかし、中学生くらいの女の子が4人しかいません。
他の地区では、小学1年生から中学2年生までの女の子がそろうので、不思議に思って
「他のお子さんは手伝わないのですか?」と聞くと、
「今年は中学2年生の女の子だけだよ。」
と教えて頂きました。
子どもの人数が少ない年には、小学生がお手伝いをする事もあるそうですが、基本的には中学生ぐらいの女の子が中心になって行われるようです。
お話を伺ったところ、
「昔は、中学2年生(14歳)というと立派な大人だった。すぐにお嫁に行くので「娘別れ」※1の意味もあった。」
「地区から外へお嫁に行った娘さんが里帰りする理由にしていた。 実家に帰るには良い理由で、一晩楽しく過ごしたものだ。」
という事でした。
観音講というひとつの行事にも、いろいろな側面があるんですね

※1 結婚の行事の一つ:かため、結納、娘別れ(お茶講)、結婚式、披露宴
参考:幕末・明治の肥前 こぼれ話 「娘別れ」
この地区の観音講には、引継ぎの為のノートがあり、毎年掛かったお金の計算、感想、反省点が、次の年へ引き継がれています。

祭りの準備
お祭りの準備は懇志(お布施)集めから始まります。早めに集め始めて、4~5日かけて集めたそうです。
引継ぎのノートにも「懇志は早めに集め始めたほうがよい」と
ほとんどの年の反省に書いてありました。
経験が生かされていますね。
当日、お堂の掃除。

観音堂は新築されたばかりという事で、とても綺麗です。
4人で掃き、拭き、と掃除を進めていくとすぐに綺麗になりました。
観音様の前掛けは、毎年観音祭りの際に新しくされています。

今年は裁縫の得意な女の子の手作りです。
自ら観音様にかけています。
頑張っていたのは手水鉢。

この大島の菅原神社には、水道がなく、隣のお家からバケツで何度も水を運び、ごしごしとたわしで洗っていました。

最後には栓をして水を貯め、参拝者が綺麗な水で手を洗えるようにします。
暑い中での作業で汗びっしょりになりながら頑張っています。
女の子たちがお掃除をしている間、お母さんたちは、炊いたお豆のパック詰めです。

お豆は、他の地区と違い「小豆」。他では金時豆なので珍しいですね。

十年ぐらい前は「唐豆」を各戸から集めて炊き、お土産にしたそうですが、今では唐豆を造っているところはないので「お金」を集め、小豆を炊くようになったそうです。
また、食べやすいよう、袋ではなくパックに詰めてお土産にします。
今年は100パックほど準備されました。

掃除を終えた女の子たちが合流してきました。

パックされた豆をクーラーバックに詰め、瓦せんべいは、参拝者に配りやすいようにバラにして箱に入れ、準備完了です。
日暮れ、いよいよ本番
午後7時。提灯に火を入れて参拝客を待ちます。

日が落ち始めた頃、子ども達の「お参りに来てください」という放送を聞いた地区の方が、続々と参拝にやってこられました。
まずは、神社の本堂、続いて境内にある観音堂へお参りです。


参拝に来られた方には、浴衣に着替えた女の子達が、冷たいお茶と瓦せんべいでおもてなし。
お土産には、先ほど準備した小豆が手渡されています。


この日は、とても蒸し暑い夜だったので、冷たいお茶は喜ばれていたようです。
参拝客の中には、これまでに観音講を経験してきた、「先輩」達や、これから観音講を担う「後輩」達の姿も。

特に、小学生の女の子たちには、
「あんた達は、今度これをせんばとやけん、お姉ちゃん達を見て勉強せんばよー」
と声がかかっていました。
こうやって次の世代にバトンタッチして、行事が続いて行くんですね

大島地区の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました!

この記事へのコメント
引継ぎ日誌があるのが、部活動のようでほほえましいですね。
子供たちが、協力してくれているのが、頼もしく感じました。
各神社でお祭りの内容が微妙にことなるのが面白いですね。
子供たちが、協力してくれているのが、頼もしく感じました。
各神社でお祭りの内容が微妙にことなるのが面白いですね。
Posted by よねりん at 2011年08月26日 18:33
いつもコメントありがとうございます。
同じお祭りでも、それぞれの地区で微妙に異なるので、その違いを見つけると、その土地ならではの地域性を垣間見れた気がして面白いです。
そういう地区の特徴も含めて、いつまでも引き継がれていって欲しいですね。
同じお祭りでも、それぞれの地区で微妙に異なるので、その違いを見つけると、その土地ならではの地域性を垣間見れた気がして面白いです。
そういう地区の特徴も含めて、いつまでも引き継がれていって欲しいですね。
Posted by 神埼市デジタルミュージアム準備室 at 2011年08月29日 09:49
at 2011年08月29日 09:49
 at 2011年08月29日 09:49
at 2011年08月29日 09:49