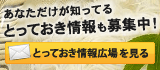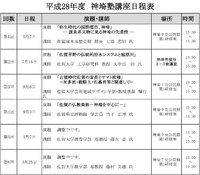乙南里の柴取り
2012年03月15日
神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 17:05 | Comments(0) | 行事
1月8日(日)、千代田町、乙南里地区の柴取り行事の取材に伺いました。

乙南里地区では、「正月に各家は玄関や小屋の入り口などに柴(シバ)を飾り、一年間の火難除けを願う」という行事を、伝統的に続けています。
地区の男の子(小1から中2)が、1月4日に行われる八天神社の祈年祭の日に合わせて八天山山頂に登り、シバを採って、地区の各家に配ります。
今では、子供会の行事に変わり、保護者と子供たち行っており、日程も1月の第1日曜日と変っています。
柴で火難除け

乙南里地区では、「正月に各家は玄関や小屋の入り口などに柴(シバ)を飾り、一年間の火難除けを願う」という行事を、伝統的に続けています。
地区の男の子(小1から中2)が、1月4日に行われる八天神社の祈年祭の日に合わせて八天山山頂に登り、シバを採って、地区の各家に配ります。
今では、子供会の行事に変わり、保護者と子供たち行っており、日程も1月の第1日曜日と変っています。
柴取り当日
朝8時半、公民館前集合です。
昭和11年に小学校1年生だった方にお話を伺うと、当時は先輩に連れられ、子供だけで歩いて朝日地区の八天神社までいったそうです。
現在は出発地点の八天神社まで車で向かいます。

神社に行く前にトイレを済ませ、準備運動。

八天神社で、一年間の家内安全と五穀豊穣をお祈りします。
いよいよ

険しい山道を子供たちもがんばって登ります。

というか…、子供たちは身軽で、私はついていけません。
ゆっくり登ります。
しばらく登ると、ようやく八天神社上宮に着きました。

とてもすばらしい眺望です。
巨石の上で記念撮影。


柴取り
八天山上宮。

上宮で、みやき町中原からいらした登山者の方から、「私たちの地域でも、火難除けに八天山の柴をとりに行く行事があるよ。2月だけどね。」と教えて頂きました。
神埼市だけでなく、近隣でも同じ行事をされているところがあるのですね。
神埼の乙南里だけでなく、もっと他にも同じ行事をされている所があるかもしれません。
これより上、頂上近くで柴をとります。
柴取りは男性の仕事です。

下山

下山すると、取ってきた柴を、地区の40軒あまりに、手分けして配ります。
「八天山の柴です。どうぞ」
「ありがとう。今年もお疲れ様。」
「私も子供の頃、弟達と登りました」
長く続く行事なので、経験者が多数いらっしゃいます。


毎年、子供たちが柴を届けるのを皆さんとても楽しみにしています。
一年一年、子供たちの成長を見る楽しみがあるのでしょうね。
子供たちも、声をかけてもらって、自然と、地域の人々に親しみを感じ、生まれ育った地域に愛着を持って育っていくのでしょう。
「伝統行事を守る」ということが、異世代間の交流の役目を担っていていることを、強く感じました。
八天山と信仰
芝取りに登る八天山は、古来より山岳信仰、修験の霊山として崇敬を集めていた山です。
山の中腹にあった中宮菩提寺(ぼじやしさん、ぼじゃーさん)は摩利支天を祀り、『父母に不孝の罪を減じ、火難を除す』といわれていました。(昔は子供だけで登ったというのは、この『父母に不孝の罪を減じ』という謂れがあったからでしょうか。)
明治時代に入ると、修験道廃止令により、麓の坊(修験者の宿舎)が八天神社へと変わり、現在に至っています。
八天神社の祭神は火結神を祀っており、鎮火、防火の神として県内のみならず、県外からも参詣者は多く来られますが、一般には、神社の祭日、特に祈年祭に参拝登山者が多いそうです。
元々、この柴とり行事も祈年祭にあわせて行っていたということでした。
祈年祭とは、「としごいのまつり」といい、毎年旧暦2月4日に行われる一年の五穀豊穣などを祈願するもので、11月の新嘗祭(収穫祭)と対になる神道の祭祀です。
新嘗祭に比べるとあまり知られていないのですが、稲穂を蒔く季節の初めにあたって、その豊穣をお祈りする大事なお祭りの日なのです。
そういう大事な日に八天山(霊山)に登り、柴をとってきて、各家の玄関に飾るというのは、火難除というだけでなく、同時に家内安全、五穀豊穣を祈る大切な行事だったのかもしれません。
取材協力ありがとうございました。